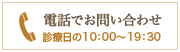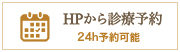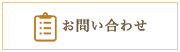歯医者と矯正歯科の違いとは?どちらを選ぶべきか徹底解説!
24.11.08
カテゴリ:BLOGインビザラインマウスピース矯正ワイヤー矯正一般歯科予防歯科治療矯正歯科
歯医者さんと矯正歯科の違い 歯医者さんと聞くと、むし歯の治療をする病院をイメージする人が多いと思います。では、歯科矯正治療を受けたい時にはどのようにして歯医者さんを選べばいいのでしょうか? また、歯科医院や歯科医師はなぜ「歯医者さん」と呼ばれるのでしょうか? その疑問にもお答えします。 「これから歯医者さんに行くよ」と聞くと、「今から歯科医院に行くんだな」と分かると思います。むしろ、「今から歯科医院に行くよ」の方があまり聞いたことがないような気がします。 歯医者さんとは、歯科医院や歯科医師の事を親しみの込めた呼び方です。 歯科医院や歯科医師はもちろん正しい名称ですが、なんとなくお堅くてすこし真面目な印象ですね。 内科などの医師の事を「医者」と呼ぶのと同じように、歯医者は『歯の医者』という意味で使われています。 しかし実は、医師と医者というのは同じように使われてますが、実は厳密にいうと違います。 医師は医師国家試験に合格し医師免許を持っている人のことをいいます。 歯科医師は、歯科医師国家試験に合格して歯科医師免許を持っている人のことです。 また、医者とは、病気やケガを治療をする人のことをいいます。 日本では医師免許や歯科医師免許を持っていないと病気の診断や治療はできないので、医師と医者はほぼ同じ意味です。 たとえば、漫画の中に登場してくる「ブラックジャック」は医師免許を持っていないので医師ではなくて医者ですし、「おもちゃのお医者さん」は免許をもっていないので「おもちゃの医師」とは違います。 また、歯科は昔はむし歯治療で通う患者さんがほとんどだったので、歯を削ったり抜いたりするような治療のイメージが強かったと思います。そのため、少し怖いイメージもあったのかもしれません。 それを和らげるために、少し優しく聞こえる「歯医者さん」という言葉が多く使われているのかもしれませんね。 しかし今は、むし歯治療以外の目的で歯科医院に通う患者さんが増えています。 矯正歯科は、矯正歯科治療を専門的に行っている歯科医院です。 矯正歯科治療とは、 ・口の周りの外観(見た目)が気になるので、歯並びなどをきれいにしたい ・咬み合わせを良くしたい ・顎が痛くなりやすい(顎関節症)ので、症状を改善したい などの理由で、歯の位置や向きを移動したり上下の顎骨の位置などを調整してお口の中の状態を改善していくための歯科治療です。 矯正歯科治療は、主にワイヤー矯正治療法とマウスピース矯正治療法が使われています。 ワイヤー矯正治療法は、歯にブラケットという器具を装着して、ブラケットのフックにワイヤーとゴムをかけて繋げることで、ゴムのけん引力を使って歯を動かしていく治療法です。 1か月に1度くらいのペースで歯科医院に通い、ワイヤーとゴムをかけなおしたりメンテナンスをします。 ワイヤー矯正治療の場合は自分で器具を外したりすることはできません。そのため、歯ブラシなどでの歯の清掃がうまくできず、むし歯や歯周病になってしまうリスクが高くなってしまいます。器具が口の中の粘膜や舌に当たって傷になったり、ゴムの引っ張る力が強いと痛みがでることもあります。 また表側に矯正器具をつけている場合には、外から口元を見た時に目立ってしまうこともあります。 マウスピース矯正治療法は、透明なマウスピースを1日のうちの決められた時間に装着し、歯を動かしていく治療法です。 シリコンを口の中に入れた歯型を基に作った模型を使い、患者さんそれぞれのお口の中にあわせたマウスピースをつくります。 定期的に歯科医院で歯のクリーニングなどのメンテナンスを受けながら、歯科医師の指示通りにマウスピースを交換していくことで、少しずつ歯の位置や向きを整えていきます。 マウスピースは自分で取り外しをすることができるので、食事や激しい運動をする時には取り外すことができます。また、歯ブラシなどお口のケアをする時にも外すことができますし、マウスピース本体も洗うことができるので清潔に保つことができます。 そして、マウスピース矯正治療法はワイヤー矯正治療法ほど強い力で引っ張るわけではないので、痛みも少ないのが特徴です。 マウスピース矯正治療法のなかでも、今注目されているのがインビザライン矯正です。インビザライン矯正は、患者さんのお口の中を3Dスキャナーで取り込み、そのデータを基にお口の中の細部まで3Dデータ化することができます。シリコンをお口の中に入れて型取りなどをしなくても、より精密な歯型を取り込むことができます。 また、現在のお口の中の状態からどのようにして理想の状態に近づけていけばよいのかをPCを使ってシミュレーションしながら医師と相談して決めていくことができるので、完成図も確認出来て安心です。 定期的に歯科医院でメンテナンスをうけながら、歯科医師の指示に従い10日から2週間ごとに新しいマウスピースに交換していきます。マウスピースを装着するのは1日22時間以上と決められているので、食事や歯磨きの時などは外すこともできます。 プルチーノ歯科・矯正歯科では、お口の中をカメラで撮影して矯正治療後の歯並びのシミュレーションを見ながら無料矯正相談を受けることができます。 インビザライン矯正の認定を取得したインビザドクターの無料相談をぜひ受けてみてください。 では、歯科と矯正歯科はどうちがうのでしょうか。 歯科には「科目」と呼ばれるものがあって、それによってどのような治療を専門にしているのかが分かるように分けられています。 矯正歯科や口腔外科、小児歯科などがそれに当てはまります。 歯科というと、歯を削ったり被せものをつけるむし歯治療や歯周病予防の為の歯石除去や歯ブラシ指導などを想像するのではないでしょうか。 むし歯や歯周病の治療は「一般歯科」とよばれています。一般とは、「一番広く知られている」という意味です。むし歯の治療や歯周病治療は老若男女関係なく、多くの人が受ける事がある治療なので、このように呼ばれているようです。 もちろん、むし歯治療や歯周病治療にも多くの治療法があり、患者さんによって受ける治療は違いますが、一般歯科治療は多くの歯科医院で行われています。 矯正歯科治療は、お口の中の環境を大きく変えるため、多くの知識と専門的な技術と設備が必要です。また、一般歯科治療にくらべると、費用も高くて治療時間も長くかかります。 そのため、矯正歯科治療を受けるときには矯正歯科治療の専門的な知識と積み重ねられた経験と技術が大事なのです。そのような知識や技術を持っている歯科医師の事を専門医とよびます。 さらにインビザライン矯正の治療には、インビザライン矯正に関する専門的な知識も重要です。矯正歯科治療に関する深い知識と、多くの経験により卓越した技術を持ち、なおかつインビザライン矯正の経験が一定以上あると認められた歯科医師は、インビザドクターに認定されています。 プルチーノ歯科・矯正歯科には、インビザドクターに認定された歯科医師もいますので、安心してインビザライン矯正を受けることができます。 歯医者と歯科医にはあまりはっきりした違いはありませんが、多くの人が親しみを込めて歯医者と呼んでいると思います。これからも親しみを持って安心して歯科医院に通えるように、あなたの受けたい治療をしてくれる自分にあった歯科医院をみつけてください。 プルチーノ歯科・矯正歯科では、24時間webから予約をとることができます。むし歯治療や歯周病治療のことでも、インビザラインなどの矯正歯科のことでも治療相談を受け付けています。
記事を見る
矯正歯科のロゴについて 診察券や看板などに、オリジナルのロゴを印刷した矯正歯科が増えてきています。 それはなぜでしょうか? また、矯正歯科のロゴにはどんなサインが隠されているのか説明したいと思います。 あなたは入るお店や通う病院のメンバーズカードや診察券をお財布から探すときに、何を目印にしていますか?色やイラストなど、特徴的なものを目安にしている人もおおいのではないでしょうか。 そういう時に大事なのが、それぞれのお店や病院の特徴を生かしたオリジナルのロゴマークなのです。 周りをよく見てみると、お店の看板からスーパーの棚にある商品にいたるまで、いろんなマークや文字が書いてあります。これは、そのお店がどんなお店なのかやこの商品はどんな商品なのかを見ただけでなんとなくイメージできるように作られています。また、その他のお店や商品との区別にも使われています。 ロゴは、英語では「logo」と書きます。ロゴタイプという言葉の略称で、団体や会社、商標や商品名などのイメージを図にしたものです。文字と図形が一緒になっていたり、様々なタイプのものがあります。ロゴマークやシンボルマークもその中に入ります。 シンボルマーク 会社や団体、個人や家系などを象徴した記号のことで、家紋もこれに入ります。 文字を変形させたり、図だけでイメージ化したもののことです。 抽象的な物も多いので、それだけでハッキリとイメージできるものは少ないです。 しかしアップル社のリンゴやナイキのマークなどは、そのシンボルを見ただけでだいたいの人が会社のイメージが思い浮かぶのではないでしょうか。 シンボルマークは、「象徴」の英訳「シンボル」と「記号」の英訳「マーク」が合わさってできた和製英語です。 ロゴマーク 企業や商品のブランドのイメージを図案化したもので、イメージを強調したロゴやシンボルマークの中に文字が入っているものの事をいいます。絵の中に文字が一体化して入ったものや、文字が変形したような図で、会社や団体のオリジナリティを表現しています。 ロゴマークも、「ロゴ」と「マーク」をくっつけてできた和製英語です。 ロゴを作る時のイメージの決め方は、大きく二つあります。 ①お店の名前や商品の名前から連想するイメージ お店や商品の名前のイメージから図を作ったり、文字からイラストを作ります。例えば、「スマイル」という単語から笑顔のイラストやスマイルという文字を装飾して作る方法です。 この方法は、お店の名前や商品名を覚えて欲しいときに効果的です。 ②商品の内容や病院の診療内容から連想するイメージ お店で売っている商品や、診療内容から思い浮かぶイメージでイラストや記号を作ります。たとえばケーキ屋さんならケーキの絵をいれたり、内科の場合は心音を聞く聴診器をモチーフにしたりする方法です。 そのお店でどんな物が売っていたり、どんな治療を行っている病院なのかを分かりやすく伝えることができます。 このように、ロゴを作る時には「名前」や「内容」からのイメージを基に図案を作っていきます。 最近では素人でもPCのイラストソフトを使うことで簡単に作ることができます。ですが、お客さんや患者さんにより伝わりやすくしたい時には、やはり専門のクリエイターに依頼して作ってもらう方がより効果的です。 では、矯正歯科の場合はどんなロゴが使われているのでしょうか。 公益財団法人 日本矯正歯科学会のロゴマーク 日本矯正歯科学会のロゴマークは、学会名の英語表記「Japanese Orthodontic Society」から頭文字をとった「JOS」をイメージしたものです。日本を代表する国際的な矯正歯科の団体である事を強く象徴するように、「O」の文字を中央に円として描き、日本の国旗をイメージしています。 インビザラインシステムのロゴマーク インビザラインシステムは世界各国で使われている最新のマウスピース矯正システムです。患者さんのお口の中の情報を3Dスキャナーで取り込み、専門的な知識と技術を持った矯正専門医と相談しながら理想の歯並びのイメージ画像を作ります。そのイメージ画像どおりに歯並びをそろえるためのマウスピースを作り、専門医の指示通りに1日20時間以上装着することで理想の歯並びに矯正することができます。 インビザライン矯正のマウスピースは食事や激しいスポーツをする時など自分の好きな時に取り外すことができ、食後などには洗うこともできます。 また、透明なマウスピースなので装着している間も目立たず、違和感も少ないのも重要なポイントです。マウスピースは専門医の指示のもとで新しいものに取り換えていくため、清潔なものを使い続けることができます。 インビザラインのロゴは、英語表記の「invisalign japan」の文字と、白くキレイにならんだ歯をイメージした様な花びらのマークでできています。invisalignは、「invisible(見えない)」と「align」をくっつけた造語で、ロゴは「invis」までが薄い文字で書かれていて、見えないマウスピースを象徴しているようです。 画期的なマウスピース矯正治療のインビザラインシステムを提供しているのは米国のアライン・テクノロジー社(Align Technology, Inc.) で、日本法人はインビザライン・ジャパン株式会社となっています。インビザライン・ジャパン株式会社のロゴは、アライン・テクノロジー社のロゴをモノクロにしたデザインになっています。色を変えることで、日本法人オリジナルのロゴにしてあります。 プルチーノ歯科・矯正歯科のロゴマーク プルチーノ歯科・矯正歯科のロゴマークは、どのようにできているのでしょうか。 プルチーノ歯科・矯正歯科の”プルチーノ”はイタリア語で、「雛鳥」を意味します。 雛鳥というのは、生まれて間も無く初めて見たものを母鶏と認識し、色々なことを教わって成長していきます。 当法人は、患者様にとってもここで働くスタッフにとっても「こんな歯科医院は初めて」と感じていただける歯科医院を目指して日々成長し、関わる全ての方の人生のターニングポイントとなる歯科になりたいという想いを込めて、プルチーノ歯科・矯正歯科という名前にしております。 そして、その雛鳥が成長すれば、「鸞」(鳳凰)だったということから、優秀な人材が、人生のターニングポイントを求めて、またそのような組織や理念を一緒に創るために集結してくる、願いをこめて法人名は、「鸞翔鳳集」という言葉から、鸞翔会としております。 ロゴは「雛鳥」と「歯」、そして創業の鶴田祥平のSと、小川茉莉亜のMを織り交ぜた意味になっています。 プルチーノ歯科・矯正歯科では、24時間webから予約を受け付けております。矯正歯科治療やインビザライン矯正に興味をお持ちの方は、ぜひプルチーノ歯科・矯正歯科の無料相談をうけてみてください。 インビザライン矯正などの矯正歯科治療の専門的な知識と技術を持った専門医が対応いたします。
記事を見る
顎変形症とは 顎変形症(がくへんけいしょう)とは、上下の顎骨の形や大きさ、位置などのバランスの異常によって起きる、顔の変形や咬み合わせの問題(不正咬合)などの症状が起きている状態の総称です。 ①下顎前突症(かがくぜんとつしょう) 顔を横から見た時に、下顎が上顎よりも前に突き出している状態で、三日月の様にも見えます。 日本人の顎変形症の中では一番多く、「受け口」や「しゃくれ」と呼ばれることもあります。 歯の咬み合わせは通常は上の歯が下の歯に少しかぶさるようになっていますが、下顎前突症の場合には下の歯が上の歯にかぶさるようになることがよくあります。(反対咬合) ②上顎前突症(じょうがくぜんとつしょう) 顔を前から見た時に、下顎の位置よりも上顎が前へ突き出して見える状態です。これも日本人に多くある症状で、「出っ歯」などと呼ばれる状態です。 上顎前突症の場合には、上の歯が下の歯にかぶさり過ぎてしまう状態(過蓋咬合)になる事があります。 また、口を開けて笑った時に上顎の歯茎(ピンク色の歯肉)が目立つ(ガミースマイル)ことがあります。逆に口を閉じていても自然に口が開いてしまう(開口)ことがあります。 ③小下顎症(しょうかがくしょう) 下顎の骨があまり発達せずに小さく、横から見ると下顎が引っ込んだように見えます。顎が小さいので歯が並ぶスペースがあまり無いことが多く、歯並びが悪くなる事がよくあります。 ④開口症 奥歯は問題なく咬めているのに、上下の歯と歯槽骨が前に飛び出している状態。口もとが突き出たようになり、口を閉じるのが難しくなります。無意識に口が開いてしまうのも特徴です。 顎変形症によって現れる症状 顎変形症では咬合不全が起きやすくなりますが、自覚症状が出にくい場合があります。それは、わたしたちの体にはうまく機能していない器官を他の器官で補おうとするからです。 この場合は顎の機能を口の中の機能が補おうとして、無理やり咬み合わせがあった状態にしようとします。しかし無理に咬み合わせていたとしても、それに伴う症状は出てきてしまいます。 ・上手く食べ物を咬んだり飲み込むことができない(摂食嚥下障害) 口から食べ物を取り入れると、歯で咬んだり舌ですりつぶし唾液と混ぜることで食塊を形成します。 顎変形症になると、咬み合わせが上手く合っていないので食べ物を咬んで小さくするのが難しくなり、舌も動かしにくくなるため食塊を形成するのが難しくなります。 食塊が上手く形成されていない状態で飲み込もうとすると、喉や食道に大きな負担をかけます。また、食物を分解して吸収するのも難しくなってしまい、胃などの内臓にも大きなストレスをかけます。 また、麺類などを噛み切るのが難しくなります。 ・言葉の発音がしにくい(構音障害) 口を上手く閉じるのが難しい場合、音によっては発音が難しい場合があります。 また、舌の動かし方にも影響が出てくるので発音しにくいことがあります。 ・気付くと口が開いているので、口の中が乾燥しやすい(ドライマウス) 咬み合わせが上手く合っていないと、自然と顎が開いてしまうことがあります。 そのせいで口の中が乾燥してしまい、細菌などが喉に入りやすい状態になってしまいます。また、むし歯や歯周病の原因となる細菌が繁殖しやすくなるため、むし歯や歯周病のリスクも高くなります。 ・顎関節に痛みが出る(顎関節症) 咬み合わせが上手く合っていない状態で物を噛んでいると、無意識に顎に負担をかけてしまいます。 その状態が続くと、口を開けたり噛みしめるときに顎に痛みが出てしまったり、上手く動かなくなってしまうことがあります。 ・無呼吸症候群やいびきの原因になる 睡眠中は筋肉が緩みやすくなるので、噛み合わせなどに問題があると口が開きやすくなります。 また喉に舌が落ちやすくなり(舌根沈下)、それらが原因で無呼吸症候群が起きてしまったりいびきの原因になることが考えられます。 これらの症状があると、睡眠の質が低下してしまい日中の活動にも支障がでることがあります。 ・衝撃を受けると顎が骨折しやすい 人は外からの衝撃を顔に受けそうになった時、無意識に歯を食いしばり顎を固定します。しかし、咬み合わせが上手くいっていない場合はうまく食いしばることができず、顎に衝撃が伝わってしまいます。このことから、顎変形症が無い場合に比べると顎の骨折の可能性が高くなるといえます。 顎変形症になる原因 顎変形症は上下の顎骨の大きさバランスが整わないことでおこりますが、多くの場合で原因は不明です。 影響を与える事としては、遺伝や口唇口蓋裂(こうしんこうがいれつ)などによる先天性の要因と、舌の癖や指しゃぶり、事故によるケガなどの後天性の要因が考えられます。 先天性の要因の場合は小さなころから異常が明らかになる場合もありますが、顎骨は20歳くらいまで成長を続けるため年齢を重ねてから異常が分かることもあります。 また、近親者に顎変形症の病歴がある場合には、事前に予測することもできます。 顎変形症の予防策としては、指しゃぶり、頬杖などの癖をやめることも重要です。 顎変形症の診断 顔は多くの部位から作られているので、関係する診療科(矯正歯科、口腔外科、形成外科など)がそれぞれの分野で検査した結果を持ち寄った総合的な結果から、顎変形症に関する正確な診断が下されます。 検査内容としては、口腔内(口の中)の診察、噛み合わせの検査、頭部レントゲン撮影、CT撮影などがあります。外見や骨格からの評価と、機能的な評価を総合し診断し、治療計画がつくられます。 顎変形症の治療 治療に関しても、外見の治療と機能的な治療の両面から行われます。顎の位置を正常に戻すことで顎変形症の症状が改善することもありますが、噛み合わせの修正や舌の動かし方などの機能訓練が必要な場合もあります。この場合は、言語聴覚士のリハビリなど多職種との連携も必要になる事が考えられます。 顎変形症の主な治療法としては、外科手術と歯科矯正治療が行われます。 1.外科手術 顎の形成が必要な場合には、「骨切術」という手術がよく行われます。 この手術は、手術痕を目立たなくするために、多くの場合口の中から行います。 顎の骨を小さくする場合、余分な顎骨を切り取って前後の部分を合わせてプレートで固定します。プレートは時間がたてば自然に吸収される素材のものか、チタンプレートが使われます。チタンプレートの場合、必要に応じて後に除去手術を行います。 2.歯科矯正治療 軽度の顎変形症の場合は、顎の大きさや形を変えずに顎や歯の位置を歯科矯正治療で動かすのみの場合もあります。 また、外科手術をする場合でも手術を行う前や後に歯科矯正治療で歯ならびを整えておくことで、顎変形症の再発の予防につながります。 歯科矯正治療は、歯並びを整え見た目をきれいにする(審美的)目的の場合には、公的医療保険外の場合があります。 しかし顎変形症の外科手術を行う場合、手術の前後に歯科矯正治療をした場合には「顎変形症の治療のための歯科矯正治療」であると認められるため、公的医療保険が適用されます。 顎変形症の影響は、顎だけではなく口の中の機能にも影響があります。顎変形症の疑いや気になる症状がある場合には、歯科医院などで相談してみてください。 プルチーノ歯科・矯正歯科では、24時間webで診療予約をおこなっています。 歯科矯正治療の専門医が、あなたにあった治療法についてくわしく説明いたします。顎の症状や歯科矯正のこともお気軽にご相談ください。
記事を見る
日本は世界で少ない国民皆保険制度を取り入れた国 「国民皆保険」という言葉を知っていますか?これは日本の医療保険の制度の事で、「原則として日本国民全員が公的医療保険に加入し保険料を支払うことで、医療行為を受ける時のお互いの負担を軽減する制度」の事です。 「自助・共助・公助」でいうところの、「共助」にはいります。また、医療保険制度の安定のために税金も使われているので、「公助」でもあります。 海外の多くの国々では、医療保険の加入は個人でのみ行うもので入っていないという人も多くいます。そのため、同じ医療行為を受けたとしても負担金が大きく違ったり、場合によっては医療行為を受けることができないこともあります。 このような海外の国々に比べると、日本は医療行為を安心して受けることができます。 日本に住んでいる人は、基本的に国民健康保険や共済保険、社会保険健康組合保険などの、公的医療保険に加入しています。どの保険に加入するかは勤め先や年齢にもよって違いますし、負担する毎月の保険料に関してもそれぞれ違います。 また、病院の窓口で支払う治療費の負担割合も人によって違います。 保険料や負担割合は、その人の年齢、家族構成や経済状況などによってそれぞれの医療保険組合が決定しています。 公的医療保険を使って診療を受けることができるのは、保険医として認められた医師による治療のみです。そして、保険医が医療行為を行う医療機関の事を保険医療機関といいます。 保険医療機関に診療の対価として支払われる費用の事を「診療報酬」と呼び、医療行為ごとに厚生労働大臣が定めた保険点数を合算していくことで、算出します。 保険点数は「1点=10円」と定められていて、全国どこでも同じように適用されます。 こうして算定された診療報酬のうち、患者さんの加入する医療保険組合が定めた負担割合の金額を窓口で受け取り、残りは医療保険組合に申請して支払ってもらうのです。 この申請のことを「保険請求(レセプト請求)」と呼びます。保険請求は翌月の10日までに各保険組合に申請を出して受理されると、診療報酬を受け取ることができます。 保険医療機関の窓口で保険証やマイナンバーカードの提示を求められるのは、その人がどの医療保険組合に加入しているのかと負担割合を確認するために重要なことなのです。 公的医療保険に定められている治療内容(保険医療)は限定されていて、場合によっては希望したような医療行為を受けることができないこともあります。 保険医療では、「この傷病名の場合は、この治療」という風に、傷病名ごとに行える治療内容が限定されています。保険医療に適用される治療は、「多くの人が該当する治療法である」などいくつかの条件によって定められています。 これは、公的医療保険が加入者の支払っている保険料から診療報酬を支払うため、できるだけその診療報酬の金額を高くしないためのものです。 例えば、『がん治療のために新しい治療法を受けてみたいけど、その治療法がまだ新しくて効果が必ずでるとは認められておらず、公的医療保険に定められていない』などの場合には、患者さんが全ての医療費を支払う必要があるので、高額な医療費を負担することになります。 このように、公的医療保険外の医療行為を「保険外医療」といいます。 その他には、「肌をきれいにしたい」や「脱毛したい」など見た目をきれいにするための医療行為は、『ケガや病気が理由ではない医療行為』に該当するため傷病名をつけることができません。この様な場合には、保険外医療とみなされます。 保険外医療は患者さんご自身の費用負担は大きくなりますが、そのかわり自分に合った自由度の高い医療行為を受けることができるというメリットもあります。 歯科では、保険医療と保険外医療の内容はどのように違うのでしょうか。 歯科医院で行う治療に関しては、他の診療科よりも保険外医療を使う場面が多くあると思います。 たとえば、インプラント治療も保険適用はされません。インプラント治療は歯を失った箇所に金属などの素材で作られた土台を顎骨に埋め込み、その上に被せものをつけるといった外科手術が必要な治療です。 しかし、歯を失った場合にはインプラント治療以外にも「入れ歯」や「ブリッジ冠」などの保険適用になる治療法があります。入れ歯やブリッジ冠は外科治療をする必要がなく、安全性も高いので多くの人が受けている治療法です。インプラント治療は、現状では治療を受ける患者さんも入れ歯やブリッジ冠に比べると少なく、「見た目をきれいにするため」などの医療目的以上の理由もあるということで、保険適用外となっています。 他にも、むし歯の治療後に被せる冠に関しても保険外医療のものがあります。 前歯の冠を入れる場合には、保険適用の治療では合銀で鋳造されている前面のみが白い陶器で内側(口蓋・舌側)は銀色のままの補綴物(ほてつぶつ)を装着する処置が行われます。 医療行為を行うという意味であればそれでも問題ないですが、審美的な理由で内側も白い補綴物(セラミックなど)にしたい場合には保険外医療となります。 最近では、保険適用の補綴物のなかにもプラスチック製の前面が白くなっているものもありますが、これは強度の問題などから適用されるための条件が厳しく定められています。この場合は保険医が条件を満たしていると判断した場合のみ、保険適用の治療として認められます。 また歯を白くするためのホワイトニング治療などは、ケガや病気が理由ではなく審美的な目的とみなされるため、保険外医療となっています。 では、矯正歯科治療の場合はどうなのでしょうか。 矯正歯科治療は、保険医療と保険外医療の両方のケースがあります。 矯正歯科治療の目的は、咬合不全(咬み合わせが上手くいかず、食事や呼吸をすることなどに問題がある)の改善や顎変形症(顎が変形したことが原因で、痛みなどがある)の治療目的の場合と、見た目が悪く歯並びをきれいに直したいなどの審美的な目的の場合が考えられます。 ①「厚生労働大臣が定める疾患」が起因した咬合異常に対しての矯正歯科治療 ②前歯か小臼歯(臼歯のうち前から2本目まで)の永久歯が上手く生えてきていないことで咬合異常が起きていて、特別な外科手術を必要とする状態の場合に行われる矯正歯科治療 ③顎変形症による特別な手術をする場合の手術前または手術後に行われる矯正歯科治療 この3つに該当した場合には、矯正歯科治療に医療保険が適用されます。 しかし、この条件を満たす患者さんはあまり多くないと思われるので、矯正歯科治療を保険医療として受けるのは難しい場合が多いと思われます。 ですが、保険外医療の場合には患者さんそれぞれのニーズに合った治療方法を制限されることなく選ぶことができます。 保険外医療は必ずしも必要な医療行為では無いこともあるかもしれませんが、私達の生活を豊かにするためには必要なものだと思います。 プルチーノ歯科・矯正歯科では、痛みも少なく見た目にも目立ちにくいマウスピースを使った最新の治療法、インビザライン矯正を行っています。患者さんそれぞれのご希望やお悩みに合わせた治療を一緒に考えながら計画して行いますので、安心してご相談ください。
記事を見る
矯正歯科の歴史を知っていますか? 今では当たり前に見かける矯正歯科治療ですが、いったいいつから始まったのでしょうか? 実は、矯正歯科の歴史はとても長いのです。今回は、矯正歯科の歴史をひも解いてみたいと思います。 矯正歯科とは、顎や口腔(口の中)の機能が正常に使えるようにするために、上下の顎の形や位置を調整したり歯の位置や向きを動かす治療法です。審美(見た目)的に口の周りをきれいにするために矯正治療を行うこともあります。 顎や口腔の機能に問題があると、不正咬合や顎関節症などにつながります。 また、最近では頭痛や肩こりなどの全身症状にも関係しているということがわかり、注目されています。 それ以外にも歯並びが悪いと歯磨きなどの口腔ケアが難しくなるため、むし歯や歯周病になりやすくなります。 医学的な研究によって、「むし歯や歯周病の原因菌が認知症や心臓病などの原因になる事がある」ことが近年では明らかになってきました。 これらの事から、とても重要な歯科治療の一つだといえます。 矯正歯科に関する歴史的な記録は、古代ローマ時代までさかのぼることができます。 古代ローマ帝国は、現在から2800年ほど前の紀元前800年ころから1000年にわたり栄え、イタリア半島から地中海全域を支配したとても大きな文明でした。この文明のなかで、哲学や科学・医学などが目覚ましい発展をとげました。 古代ローマの中のエトルリアという地域で、この時代のある少女の頭蓋骨が発見されました。彼女の下の歯には前歯から奥歯にかけて金属製のバンドがつけられていて、研究者や歯科医師のあいだでは「歯の矯正が目的だったのではないか」と考えられています。 この地域に住んでいたエトルリア人は、装飾品なども多く出土していることから非常に裕福で美意識が高かったと考えられていて、この金属製のバンドも歯をきれいに並べる為の装置だったと考えても不思議ではないようです。 また、同じ時代の古代ローマの遺跡から、医師が子どもたちに対して「歯が生えてきたら、正しい位置へ指で押しなさい」と伝えたという文献が残っています。今では指で歯を押して動かすことはおすすめしませんが、この時代から歯を正常な位置に戻すという考え方は医師の間ではあったという事でしょう。 その約2000年後、1728年にフランスのフォシャールが書いた「歯科外科医 あるいは歯の概論」という本の中で、「フォシャールのバンド」と呼ばれる歯並びを広げるためのリボン状の金属装置が提案されています。 この装置が、現代の歯科矯正装置の源流になっています。 その後、矯正歯科はアメリカにわたり大きな発展を遂げます。 1880年に、キングスレーによってより実用性が高く効果的な歯科矯正装置が発表されました。 また、1900年初頭にはエドワード・アングルが世界初の歯科矯正学を学ぶ学校を開校しました。アングルはさまざまな症状に合わせた治療法を提案し、効率的に歯を動かすことのできる「エッジワイズ法」を発明しました。 エッジワイズ法は、歯の表面に装置をつけてワイヤーを締めることで歯を動かすという、今でも広く使われているワイヤー矯正治療法の基礎です。現在では歯科矯正の基本理論とされています。 キングスレーとアングルは、「矯正歯科学の父」と呼ばれています。 では、日本ではいつ頃から歯科矯正治療ははじまったのでしょうか。 日本でも、1900年ごろのアメリカでの矯正歯科学の発展に注目が集まり、留学して歯科矯正学を学ぶようになっていきました。明治から大正時代、昭和初期にかけて日本でも歯科矯正が始まりましたが、当時の日本では物資を手に入れる事が難しく実験的な物にとどまっていました。 その後、第二次世界大戦後の1950年代までは、歯科矯正治療は一般的には普及していませんでした。当時の手法では矯正装置を歯に固定するのが難しく効率的に力を加えることができなかったため、想定通りの治療成果を出すのは難しかったようです。 そのなかで、1971年に、東京医科歯科大学の三浦不二夫教授によって開発された「ダイレクトボンディング法」は、たいへん画期的な技法でした。 この技法は、歯の表面にブラケットという装置を歯科用接着剤でつけてしまうことで、器具が外れにくく効率的に歯に力を加える事ができるようになりました。 ダイレクトボンディング法は、現在では日本だけでなく世界中で歯科矯正治療法の一つである「ワイヤー矯正治療法」で使われるスタンダードな技法となっています。 ワイヤー矯正治療法は、歯にブラケットを装着してワイヤーとゴムをひっかけてその引力で歯を動かしていく治療法です。今では歯の裏側に矯正器具を装着する「インダイレクトボンディング法」なども使われるようになり、歯科矯正治療方法には多くのバリエーションが増えています。 近年の歯科矯正治療法には、大きく分けるとワイヤー矯正治療法とマウスピース治療法があります。 ここまではワイヤー矯正治療法の歴史をみてきましたが、マウスピース矯正法はどのように進歩していったのでしょうか。 マウスピース矯正法は、一日のうちの一定時間にマウスピースを歯に装着することで、少しづつ歯を動かしていく歯科矯正治療法です。ワイヤー矯正治療法のよりも目立ちにくく、取り外しをすることができるのでストレスも少なく、衛生的にも快適に治療を受けることができます。 1954年にオーストラリアのレイモンド・ベッグという矯正歯科医によって、ベッグ法という治療法が提案されました。 これは、装置の強い力によって歯を動かすエッジワイズ法とは違い、継続的に歯に弱い力をかけることによって動かす方法です。これが、マウスピース矯正治療法のベースの考え方になっています。 マウスピースを使った矯正方法の歴史はそれよりも古く、1920年頃には矯正歯科医スナイダーによってプラスチックのマウスピースを使った矯正治療が行われていました。 当初は、口の中をアルジネート印象材(粘土状の物)で型を取って模型をつくり、そこからプラスチック製のマウスピースを作製していました。しかし精密な模型を作ることは難しく、なおかつマウスピースを作製するのにも非常に時間が長くかかりました。 現在、マウスピース矯正の最新システムとして注目されているインビザラインシステムは1997年にアメリカのアライン・テクノロジー社によって開発され、世界各国で使われています。日本では、2006年から治療に導入されるようになりました。 インビザラインシステムは、開発されてから今までの20数年で研究を重ね常に進化しているシステムです。 当初は印象材を使って歯型をとった模型をコンピューターに取り込み、PCで完成図に向けての治療計画をたて、その計画にそった模型を作成し、それを基にマウスピースを作製していました。 その後、2011年ごろから口の中を直接スキャンしてデータをPCに取り込んで、それを基に3Dプリンターでマウスピースを作製することのできるシステムへと進化していきました。このシステムが開発された事により、現在ではほぼ全ての工程がデジタルで行えるようになりました。 デジタル化したことによって、模型の変形などもなく正確なデータをPCに取り込んで、患者さんの口の中を正確に再現してマウスピースを作ることができるようになりました。また、歯型を取る不快感も無いことから子どもでも簡単にマウスピースを作ることができます。 現在ではインビザラインシステムのほぼ全ての工程を歯科医院内で行うことができるようになり、患者さんが来院する回数も少なく、治療時間も短くできるようになりました。 また、患者さんと歯科医師が矯正のシミュレーションを見ながら治療計画を立てることができるので、安心して治療を受ける事の出来るシステムになっています。 これからも進化を続けていくインビザラインシステムは、マウスピース矯正の先覚者でありつつ先頭を走る存在だといえます。 プルチーノ歯科・矯正歯科では、インビザラインシステムを導入しています。また、インビザラインシステムの専門的な知識や技術を持ったインビザドクター認定医が、治療を行います。 ぜひ、24時間利用できるweb予約から治療相談を予約してください。
記事を見る