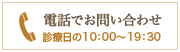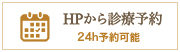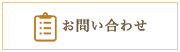こんにちは! プルチーノ歯科・矯正歯科、管理栄養士の吉田と鈴木です。 今日は、歯周病とアテローム性動脈硬化の関連をお話します! 歯周病と動脈硬化の関連は次に示す3つの説が明らかとなっています。 ①歯周病原細菌は血中を循環する。 ②歯周病原細菌が血管内でのアテローム性動脈硬化を促進する。 ③歯周組織での炎症反応による伝達因子は、血管内を含む全身の炎症レベルを上昇する。 この3つの説をもう少し詳しく書いていきます! 1.歯周病原細菌は血中を循環する 歯周病原細菌は歯の周りの歯周ポケット内で繁殖し、歯肉内に侵入します。 歯肉内の毛細血管に侵入し、血管内を循環します。 細菌の血管内への侵入は、食事や歯磨きの時にわずかではあるが常に起こっている現象です。 この血管内へ侵入する細菌の量が多く、継続的であった場合、血管内に侵入した細菌によって 活性化された血小板が固まって小さい血栓を形成することが動脈硬化の促進につながります。 歯周病原細菌のなかでも、グラム陰性桿菌(P.g)は、アテローム性動脈硬化との関連が強く 示唆されています。このP.gを認識するtoll様受容体からの自然免疫応答は、歯周病に罹患した 患者の歯周組織内で促進し、歯周組織を破壊します。 2.歯周病原細菌が血管内でのアテローム性動脈硬化を促進する 血管内に侵入したP.gが、アテローム部位で局所的に血管内皮組織などが発現した toll様受容体によって認識されて局所的に炎症反応を引き起こし、アテローム性動脈硬化の 炎症反応を促進させることも示唆されています。 3.歯周組織での炎症反応による炎症性伝達物質は 血管内を含む全身の炎症レベルを上昇させる 炎症反応が始まった歯周組織では、炎症性伝達物質の産生が促進されます。 この反応は肝臓をはじめとして全身的にも起こる反応であり、血管内の炎症性伝達物質が上昇し これらが循環することによってアテローム部での炎症反応が促進されることも 歯周病が動脈硬化を促進するひとつのメカニズムであると言える。 このようなメカニズムの複合的作用をもって、歯周病がアテローム性動脈硬化を 促進すると考えられています。 ちょっと今日の内容は難しいですが、皆さんに覚えておいて欲しいことは 歯周病菌は、口腔内だけで悪さをするわけではなく、血液にのって 血管の壁を攻撃してアテローム性動脈硬化を引き起こしやすくなってしまう! という事を覚えておいてください。 最近、歯科検診受けましたか? プルチーノ歯科では、歯周病検査の時に拡大鏡を使用しています! もちろん、LDLコレステロールの値が高い人も動脈硬化のリスクが高いので 健康診断で引っかかった人は食事内容の見直しが必要ですよ☆ プルチーノ歯科・矯正歯科でお待ちしております!
こんにちは! プルチーノ歯科・矯正歯科、管理栄養士の鈴木です。 今日は、歯周病と心血管疾患・アテローム性動脈硬化のお話の続きで アテローム性動脈硬化 とは何か?というお話。 アテローム性動脈硬化とは、動脈の内側に粥状(アテローム性)のプラーク塊が発生している状態をいいます。 動脈の内膜にプラークが発生して肥厚することにより、血液が流れる血管腔が狭くなって血液を流れにくくしてしまったり、内膜の中で成長したプラークが破綻してできた血栓が飛ぶと細い血管に詰まり(塞栓)、その先の血流を遮断してしまいます。 結果的に心臓や脳といった重要な臓器へ十分な栄養や酸素が運ばれず狭心症や心筋梗塞などの冠動脈疾患、脳梗塞などの脳血管障害を引き起こします。 歯周病とアテローム性動脈硬化の関連研究が行われ始めたのは、 口腔内だけにいるはずの歯周病原細菌がアテローム性動脈硬化のプラーク内から検出されたことによるそうです。 歯周病原細菌の媒介がアテローム性動脈硬化の促進に関連があると研究が進められています。 アテローム性動脈硬化の主たる根源は高コレステロール血症です。 高コレステロール血症の方、歯周病が関わっているかもしれません! まずは歯科検診、してみましょう☆ プルチーノ歯科・矯正歯科でお待ちいたしております♪
プルチーノ歯科・矯正歯科 院長の鶴田です。 本日より、マイクロスコープを増設して3台となりました。 開業当初よりマイクロスコープを導入し、様々な治療や説明用として使用しておりましたが、より多くの患者様に精度の高い治療を御提供出来るように、 今回マイクロスコープを増設致しました。 マイクロスコープが登場して以来、一昔前とは治療や診断の精度は格段に変わっています。マイクロスコープでしか診断出来ないこと、治療出来ないこともたくさんあります。 患者様は自分の口腔内はなかなか見えないので実感は少ないかもしれませんが、歯科医師側としてはマイクロスコープがあるのとないのとでは治療や診断のレベルは全く異なってきます。 また、マイクロスコープで撮影した画像をそれぞれの患者様に見せて説明をさせていただいていますが、実際に現状を目の当たりにすると納得感が違うと感動していただけています。 現在の口腔内の状態を高い精度で診断し、さらに視覚的に納得のいく説明を受け、より精密な治療を御希望の方はぜひプルチーノ歯科・矯正歯科に御来院ください。
こんにちは! 管理栄養士の鈴木です。 歯周病シリーズ 第二弾 は “歯周病と心血管疾患・アテローム性動脈硬化” です。 なんと、歯周病は心臓や血管の病気とも関係があるんですねー。 本日はまず心血管疾患についてのお話。 心血管疾患とは、心臓と血管の障害を広く示しています。 心臓の疾患には、心筋症、心不全、心不整脈、炎症性心疾患(心内膜炎、心筋炎)、心臓弁膜症、先天性心疾患が含まれます。 そして 血管の障害には、冠動脈疾患(狭心症、心筋梗塞)、末梢動脈障害、脳血管障害(脳梗塞など)、腎動脈狭窄、大動脈瘤を含みます。 血管障害はほとんど “ アテローム性動脈硬化 ” に起因することが多く、この “ アテローム性動脈硬化 ” の主たる根源は高コレステロール血症であるとみなされています。 高コレステロール血症は LDLコレステロール(悪玉コレステロール)の数値が140mg/dl以上のことです。 ちなみに、、、 日本人の死因(疾患による)のランキングですが 1位 悪性腫瘍(がん) 2位 心疾患 3位 脳血管疾患 ・・・、です。 日本人の死因の多くを占める疾患と歯周病が関係しているなんて! と知ったら・・・歯周病、放っておけないですよね。 歯茎がむず痒い、歯磨きすると歯茎から血がでる、歯がぐらぐらする、噛むと痛い、膿んだり・腫れたり、口臭がするなどなどの症状はありませんか? それ、きっと歯周病です。歯医者さんに行きましょう! プルチーノ歯科・矯正歯科でお待ちいたしております☆ 次回は血管障害のきっかけ、アテローム性動脈硬化についてのお話です。
こんにちは!管理栄養士の吉田です! 昨日のテレビで「糖尿病になるとどれぐらい医療費がかかるのか」 という特集がやっていましたが、皆さんご覧になりましたか? 歯周病と糖尿病の関係を勉強している私にはとてもタイムリーだったので思わず見入ってしまいました。 とある糖尿病患者の一例で、最初は月1回の診察費のみでしたが 血糖コントロールがうまくいかず投薬開始。脂質異常症も発症して追加投薬。 これが12年続き、血管への負担がピークになり脳梗塞を発症。 一命はとりとめたものの、麻痺が残ってしまった。 というものでした。 薬が増えるごとに、医療費がどんどん増えてしまいます。 それが何十年も続くとなると医療費も何百万となり負担も大きいですよね。 更に、命に関わるような病気にまで発展してしまう可能性もあるんです。 いろんなメディアで 「糖尿病にならないために、食生活や運動などの生活習慣を見直しましょう。」 というのはよく聞きますよね。 加えて、歯周病にならないよう口腔内の環境をきれいに保つことも 糖尿病にならないための大切な要素の1つです。 最近歯科検診受けてないなぁ… この前の健康診断で血糖値高めだったなぁ… とお心当たりのある方はぜひプルチーノ歯科で検診を受けてみてください。 皆さんの健康をお口の中からサポートさせていただきます!